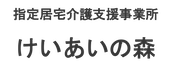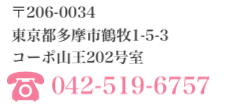- ホーム>
- 住宅改修
敬愛倶楽部の住宅改修
介護保険の住宅改修とは?
介護保険制度には、「居宅介護(介護予防)住宅改修費」という項目があります。
これは介護のために住宅改修する際にかかった費用を一部負担してくれる仕組みです。要介護認定を受けている被保険者が自宅の住宅改修を行う場合に、その工事費用(20万円まで)の7~9割が支給されます。
●支給対象となる人
支給の対象となるのは、介護保険の要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けており、なおかつ自宅(介護保険被保険者証に記載されている家)に住んでいる人です。
したがって、介護保険施設に入所している人や病院に入院中の人、一時的に住んでいる住宅などは支給の対象とはなりません。ただし、退所・退院の期日が明確であり、その後住むために自宅を改修する必要がある場合などであれば、支給金を受けられることもあります。
●支給額
介護保険の対象となる住宅改修をすると、費用の9割(一定の所得がある人は8割、とくに所得が高い人は7割)が支給されます。ただし、要支援・要介護区分に関わらず「支払限度基準額」は20万円と定められています。
つまり、改修にかかった費用のうち支給申請できるのは20万円までということです。
したがって、自己負担割合が1割の人は18万円まで、2割の人は16万円まで、3割の人は14万円まで補助金を受け取れるという計算になります。
なお、基準額の上限を超えた分については、全額自己負担となります。
また、地域によっては独自の住宅改修補助制度を設けているところもあります。そうした制度を活用すれば、20万円を超えた分に関しても補助が受けられる場合があります。
●支払い方法
支払いは基本的に「償還払い」とされています。償還払いとは、対象となる工事費用を全額事業者へ支払い、改修工事完了後にかかった費用の9割(一定以上の所得者は8割または7割)を払い戻してもらうという方法です。
ただし事業者によっては「受領委任払い」を選択することもできます。受領委任払いとは最初から費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)を支払う方法のことです。
受領委任払いを希望する場合には、「受領委任払い取り扱い事業者」に登録をしている事業者に工事を依頼する必要があります。
●介護保険の住宅改修費のメリット
住み慣れた家で暮らし続けたいと考える要介護・要支援認定者の方は少なくないでしょう。
とはいえ、身体の変化に伴って家の構造自体が生活に合わなくなってくることはしばしばあります。
そうした家の構造を住みやすいように改修することは、事故の予防につながり、自立度の向上を促すため、介護の一環として重要な意味を持っています。
また、被介護者にとってだけでなく、介護する側にとっても負担の軽減になります。
介護保険を活用すれば、こうした住宅改修の費用について大きな補助を受けることができます。
上述のように、最大18万円まで支給されるので、積極的に介護のためのリフォームを行うことができます。
支給限度基準額の仕組み
支給限度基準額は20万円と決まっていますが、その範囲内で分割して利用することができます。
また、新たに20万円が設定される例外もありますので、それらの仕組みを説明します。
●支給限度基準額の分割利用
支給限度基準額の20万を利用できる回数は原則一人につき一回と定められていますが、20万円の範囲内であれば複数回に分割することも可能です。
たとえば1回の改修工事で5万円しか使わなければ、次に15万円他の改修工事を行うことも可能です。
●支給限度基準額の利用回数の例外
上述のように、介護保険の住宅改修費の支給限度額は一律で20万円までと定められており、使い切ると終了します。
ただし、支給限度額を使い切ってしまった場合でも、次のような条件に該当すれば再度20万円まで利用できることがあります。
●要介護状態区分が3段階以上上がった場合
初めて住宅改修費を行った時点の要介護状態区分から、3段階以上重度になった場合には、一回限りで再度20万円まで受給することができます。
たとえば、要介護1と認定されている人が住宅改修費を20万円まで利用した後に要介護4と変更されれば、支給可能額がリセットされて、再度20万円まで利用することができます。
●転居した場合
転居した場合、転居以前に暮らしていた住宅ですでに介護保険の住宅改修費を使って改修工事を行っていたとしても、転居後の住宅について20万円まで受給することが可能です。
ただし、転居先の住宅を新築する場合は、住宅改修とは認められないため支給対象とはならないので、注意が必要です。
介護保険の住宅改修費が支給対象となる工事は?
介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事の種類は、厚生労働省によってあらかじめ次の6つに定められています。
「福祉用具購入」や「福祉用具貸与」といった介護保険の別の支給対象となるものは、住宅改修費の対象外となっています。
●手すりの取り付け
廊下、玄関、階段、トイレなどに手すりを付ける工事。移動のしやすさの向上や転倒防止対策に役立つものです。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなどが適切なものとされています。
ただし、福祉用具貸与に該当する手すりや紙巻器付き棚手すりなどは支給の対象外となります。
●段差の解消
リビング、廊下、トイレ、浴室などの段差や傾斜を解消するための工事。具体的には、敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げしたりといった工事が想定されます。
ただし、福祉用具購入に該当する浴室用すのこ・浴槽用すのこや、福祉用具貸与に該当するスロープ・踏み台などは支給の対象外となります。
●滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
リビング、階段、浴室などに使われている滑りやすい床材を滑りにくい床材に変える工事。
たとえば、畳敷きから板製床材やビニル床材に取り替えるなどが想定されます。
また、車椅子が使いやすいように畳の床をフローリングに変更することなども可能です。
ただし、ベッドを置くという理由でフローリング等に変更する場合は支給の対象外となります。
●引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに変更する工事。
扉の全体の取り替えだけでなく、握力が弱くなると開閉しにくいドアノブの変更や、扉を動かしやすくするための戸車の設置なども含まれます。
●洋式便器等への取り替え
和式トイレを洋式トイレに取り替える工事。立ち座りの負担を軽減し、トイレを使いやすくすることが可能になります。
また、現在使っている洋式トイレをより立ちあがりしやすい洋式トイレに取り替える工事なども対象です。
ただし、福祉用具購入に該当する腰掛便座や、暖房機能や洗浄機能の付加などは支給の対象外となります。
住宅改修費の支給申請の方法
| 1. 住宅改修についてケアマネージャーなどに相談 | まずは担当のケアマネージャーに現在の生活で支障をきたしている部分を伝え、介護保険の住宅改修費の利用を検討します。 |
|---|---|
| 2. 事業者による家の下見・改修プランの作成 | 改修することが決まったら、工事を担当する事業者に下見に来てもらいます。そこで改修の希望などを伝えます。その下見の結果を元に、事業者が住宅改修プランを作成します。 改修プランや費用見積もりなどを吟味したうえで、最終的に契約するか否かを決定します。 |
| 3. 申請書類の一部を提出(事前申請 | 工事の契約が決まったら、利用者は住宅改修の支給申請書類の一部を市区町村などの保険者に提出します。保険者は提出された書類などから、支給対象として適切かどうかを確認します。 |
| 4. 工事施工・完成 | 事前申請にしたがい工事を行います。 |
| 5. 住宅改修費の支給申請・決定 | 工事が終了したら、利用者は領収書など発生した費用のわかる書類などを保険者に提出します。その時点で、正式な支給申請が行われます。 保険者は、事前に提出された書類との照合や、工事が実際に行われたかどうかの確認などを行い、あらためて支給対象として適切かを判断します。そこで支給が必要と認められてはじめて改修費が支給されます。 |
必要な書類は?
上述の説明からも分かるように、住宅改修の支給申請にあたって必要となる書類は、工事の事前に提出するものと事後に提出するものの二種類があります。
申請書類で不明な点は、自分の住む市区町村の介護保険窓口に相談するようにしましょう。
●事前申請に必要な書類
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積もり書
・住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの
●事後申請に必要な書類
・住宅改修に要した費用に関わる領収書
・工事費用内訳
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)